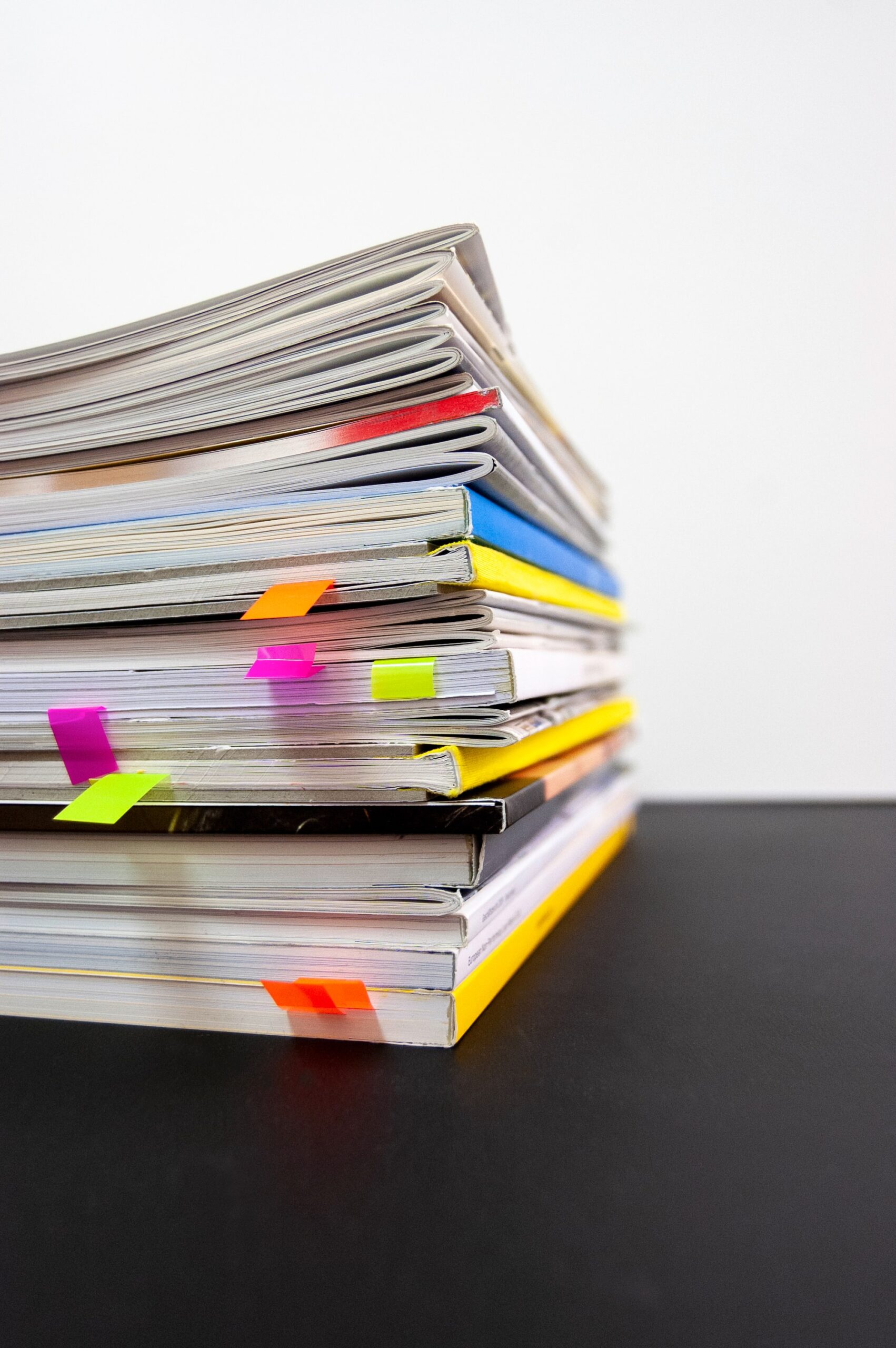相続の手続きでは遺言書がある場合などを除き、相続人全員の遺産分割協議書や印鑑証明書が必要ですが、
行方不明になっていて連絡がとれない相続人がいて手続きを進めることができないことがあります。
行方不明といっても一時的に不在にしているのではなく、
調査を尽くしてもまったく所在がわからない人がいるという場合は、
家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」の申立てや「失踪宣告」の申立てをする方法があります。
「不在者財産管理人」は、行方不明になった人の財産を管理するため家庭裁判所によって選任され、
裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加したり、不在者名義の不動産の売却などの処分を行います。
「失踪宣告」は次の場合に不在者が法律上死亡したとみなす制度です。
①不在者の生死が7年間明らかでない場合(普通失踪)
→最後に確認が取れた日から7年経過した日に死亡したとみなされる
②戦争・災害などの危難が去ったあと生死が1年間明らかでない(危難失踪)
→危難が去った時に死亡したとみなされる
失踪宣告がされると不在者についての相続が開始し、不在者に配偶者がいれば婚姻関係も終了します。
行方不明になってから7年経っていない場合はまず不在者財産管理人選任の申立てをし、
7年経った時点で失踪宣告の申立てを行うケースもあるようです。
先日受けた相続登記のご依頼では、戸籍上は現在まで生存したままになっているが
戦時中に生後間もなく亡くなっている可能性が非常に高い相続人の方がいました。
そのままでは相続の手続きを進めることができないため、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした上で、
その方を除いた相続人で遺産分割協議を行うことになりました。
失踪宣告の申立てには調査や官報公告等を含め1年近くの期間がかかります。
審判が確定すると役所に届出をすることで不在者の戸籍に
「死亡とみなされる日」「失踪宣告の裁判確定日」等が記載され、
相続等の手続きを進めることができます。
2024年4月より相続登記の義務化がスタートしました。
ふるえ司法書士事務所では相続・成年後見などのご相談を初回無料で承っております。
お気軽にご相談ください。